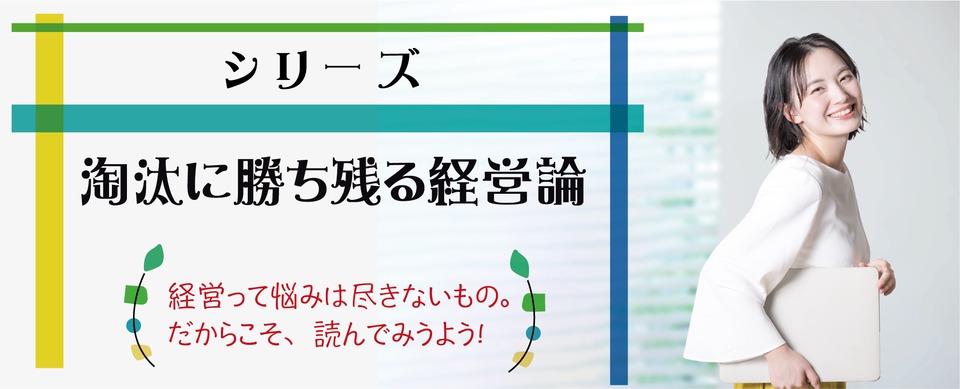第10回:首を取るな(高師直的発想法)
2008.10.01
「常識の殻を破り、豊かな発想力を手に入れたい」
こんな願望を持っている諸兄は多いであろう。
しかし、「とてもムリ」と諦めている向きも、また多い。
だが、ここは脳内道場である。
きょうも、この「常識の殻を破り、豊かな発想力を身につける」稽古をしよう。
全ての「当たり前」に疑問を持ち、逆の方向から考えるクセをつけるのだ。
あらゆる常識の逆転は、自然に起きたのではない。
『誰かが実践したのである』
今回は、前回の源義経の続きであるが、
歴史上、悪役として名高い(というのも変だが)高師直のエピソードである。
悪役ではあるが、発想の豊かさは源義経と同じなのである。
【首を取るな】
現代では「首を取るぞ」と言っても、「やってやる」というノリの言葉のひとつに過ぎない。しかし、その昔は文字どおり戦場で敵の首を取る行為そのものだったわけである。
こんなことは、常識中の常識だが・・・。
さて、本題はここからだ。
では、何のために「首を取った」のかを考えて欲しい。
敵の命を奪うのが目的であれば、槍で一突きのほうが効果的である。
第一、絶命した相手の首をわざわざ切り落としているのである。
殺生が目的ではなさそうだ。
そう、誰もが分かっているとおり、目的は「手柄の証明」である。
サムライが命がけで戦うのは恩賞目当てである。
恩賞とは土地であり、金であり、地位である。
自分が望む恩賞にふさわしい働きをしたことを証明するには、
「こんなにたくさん敵を殺した」
あるいは
「名のある手ごわい敵を倒した」ことを証明しなければならない。
それで、一番分り易い「敵の首を取ってくる」という行為が常識化したのである。
これで終わり ・・・ではない。
これでは「常識への挑戦」にならないので、もう少しお付き合い願う。
実は、この一般化した常識に挑戦した男がいたのだ。
その男こそ、高師直(こうのもろなお)である。
彼は、足利幕府を開いた足利尊氏の執事(No.2か3の地位)として、
足利政権の設立に功績のあった人物である。
その一方で、冷血非情、謀略家、色欲魔、卑怯者、往生際の悪い男として散々な評判の人物でもある。
極め付けは、忠臣蔵の吉良上野介のモデルとされてしまったことであろう。
ちなみに江戸時代は、当時の現実の事件を芝居の題材にすることが許されなかった。
そのため、作者は、時代設定を室町時代に移し、
足利の実在の人物を忠臣蔵の登場人物にかぶせて
歴史ドラマにしてしまったのである
これは、実に卓越したアイディアだと言えよう。
最初は「仮名手本忠臣蔵」という人形浄瑠璃として上演された。
大石内蔵助が大星由良之助、浅野内匠頭が塩治判官というような名前になっているのは、
この理由である。
ちなみに、大星由良之助は架空の名前である。
(名前は違っても、すぐに誰だか判るようにしてあるのもスゴイ!)
そして、吉良になったのが高師直というわけであるから、
彼がどのくらい評判の悪かった人物だったかはお分かりと思う。
しかし、筆者は、一般の「常識に逆らって」彼を高く評価している。
もっとも、部下の妻にまで手を出したと言われる彼の色欲ぶりに対してではないことは断わっておく。
冒頭の「首を取る」という常識を覆した男としてである。
人間の首は案外重いものである。
武士といえども、2つ3つの首を腰にぶらさげて戦うことは重労働で、
疲労により自分が首を取られる、という笑えない話になってくる。
しかし、大事な首は捨てられない。
ここで高師直は、「逆転の発想」で考えたのである。
武士は、首そのものが欲しくて腰にぶら下げているのではない。
欲しいのは恩賞であり、その証明なわけである。
そこで彼は自分の部隊に対し次の策を打ち出した。
「敵を倒した後、首を取ってはならない。
すぐに次の敵へ向かえ。
ただし、手柄の証明のことは心配するな。
専門の『手柄証明係り』を何人も戦場に派遣する。
敵を倒したら、彼等に申告せよ。
彼等が敵の死体を確認したら帳面に付けていく。
さあ、心置きなく戦え」
この効果は絶大であった。
首を取らない彼の部隊は、
当たり前だが、戦の後半になっても疲労が少ない。
疲労困憊の他の部隊を尻目に強力部隊としてその名を馳せた。
前回の源義経同様、常識を打ち破った「逆転の発想」の勝利である。
こんな願望を持っている諸兄は多いであろう。
しかし、「とてもムリ」と諦めている向きも、また多い。
だが、ここは脳内道場である。
きょうも、この「常識の殻を破り、豊かな発想力を身につける」稽古をしよう。
全ての「当たり前」に疑問を持ち、逆の方向から考えるクセをつけるのだ。
あらゆる常識の逆転は、自然に起きたのではない。
『誰かが実践したのである』
今回は、前回の源義経の続きであるが、
歴史上、悪役として名高い(というのも変だが)高師直のエピソードである。
悪役ではあるが、発想の豊かさは源義経と同じなのである。
【首を取るな】
現代では「首を取るぞ」と言っても、「やってやる」というノリの言葉のひとつに過ぎない。しかし、その昔は文字どおり戦場で敵の首を取る行為そのものだったわけである。
こんなことは、常識中の常識だが・・・。
さて、本題はここからだ。
では、何のために「首を取った」のかを考えて欲しい。
敵の命を奪うのが目的であれば、槍で一突きのほうが効果的である。
第一、絶命した相手の首をわざわざ切り落としているのである。
殺生が目的ではなさそうだ。
そう、誰もが分かっているとおり、目的は「手柄の証明」である。
サムライが命がけで戦うのは恩賞目当てである。
恩賞とは土地であり、金であり、地位である。
自分が望む恩賞にふさわしい働きをしたことを証明するには、
「こんなにたくさん敵を殺した」
あるいは
「名のある手ごわい敵を倒した」ことを証明しなければならない。
それで、一番分り易い「敵の首を取ってくる」という行為が常識化したのである。
これで終わり ・・・ではない。
これでは「常識への挑戦」にならないので、もう少しお付き合い願う。
実は、この一般化した常識に挑戦した男がいたのだ。
その男こそ、高師直(こうのもろなお)である。
彼は、足利幕府を開いた足利尊氏の執事(No.2か3の地位)として、
足利政権の設立に功績のあった人物である。
その一方で、冷血非情、謀略家、色欲魔、卑怯者、往生際の悪い男として散々な評判の人物でもある。
極め付けは、忠臣蔵の吉良上野介のモデルとされてしまったことであろう。
ちなみに江戸時代は、当時の現実の事件を芝居の題材にすることが許されなかった。
そのため、作者は、時代設定を室町時代に移し、
足利の実在の人物を忠臣蔵の登場人物にかぶせて
歴史ドラマにしてしまったのである
これは、実に卓越したアイディアだと言えよう。
最初は「仮名手本忠臣蔵」という人形浄瑠璃として上演された。
大石内蔵助が大星由良之助、浅野内匠頭が塩治判官というような名前になっているのは、
この理由である。
ちなみに、大星由良之助は架空の名前である。
(名前は違っても、すぐに誰だか判るようにしてあるのもスゴイ!)
そして、吉良になったのが高師直というわけであるから、
彼がどのくらい評判の悪かった人物だったかはお分かりと思う。
しかし、筆者は、一般の「常識に逆らって」彼を高く評価している。
もっとも、部下の妻にまで手を出したと言われる彼の色欲ぶりに対してではないことは断わっておく。
冒頭の「首を取る」という常識を覆した男としてである。
人間の首は案外重いものである。
武士といえども、2つ3つの首を腰にぶらさげて戦うことは重労働で、
疲労により自分が首を取られる、という笑えない話になってくる。
しかし、大事な首は捨てられない。
ここで高師直は、「逆転の発想」で考えたのである。
武士は、首そのものが欲しくて腰にぶら下げているのではない。
欲しいのは恩賞であり、その証明なわけである。
そこで彼は自分の部隊に対し次の策を打ち出した。
「敵を倒した後、首を取ってはならない。
すぐに次の敵へ向かえ。
ただし、手柄の証明のことは心配するな。
専門の『手柄証明係り』を何人も戦場に派遣する。
敵を倒したら、彼等に申告せよ。
彼等が敵の死体を確認したら帳面に付けていく。
さあ、心置きなく戦え」
この効果は絶大であった。
首を取らない彼の部隊は、
当たり前だが、戦の後半になっても疲労が少ない。
疲労困憊の他の部隊を尻目に強力部隊としてその名を馳せた。
前回の源義経同様、常識を打ち破った「逆転の発想」の勝利である。