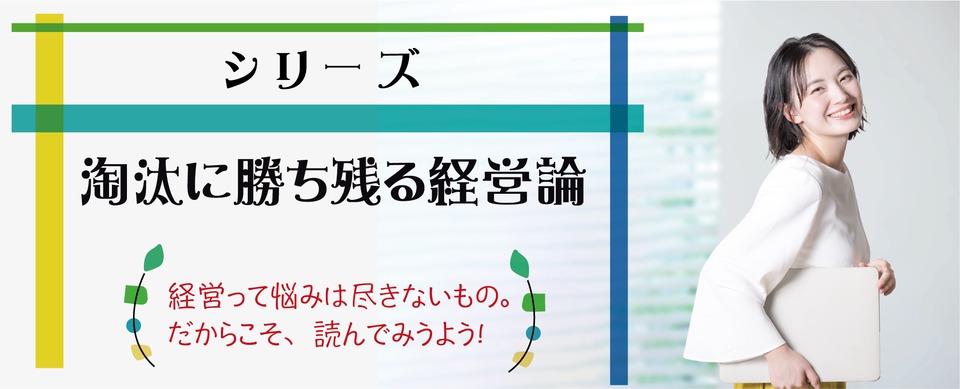第7回:おばあさんのくれた100円玉
2008.07.01
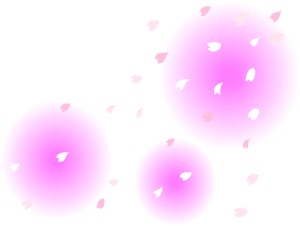
今回は私の少年時代のエピソードを話そう。
だいたい、他人の思い出話など「つまらん」ものの代表なので、
「きっとパスされる」と自虐的には思っている。
まあ・・・とにかく話を始めるとしよう。
昭和30年代の話である。
近年、映画がヒットした「always 三丁目の夕日」の世界である。
小雪や堀北真希の顔でも思い浮かべれば、
少しは読んでもらえるかな、などと思いつつ話を進める。
商店街と住宅街が入り混じる、とある街の坂道を、
小学6年の私は必死に荷物用の重い自転車を漕いでいた。
真夏の太陽が容赦なく照り付ける、うだるような昼下がりであった。
その頃、私の家は氷屋を営んでいた。
職業軍人であった父は、戦後、米軍の公職追放令によって、まともな職に就けなかった。
郷里で商売を始めたが、何をやっても武士の商法。
借金ばかりが膨れ上がり、故郷を捨てた。
単身、東京に出た父だが、思うような商売にありつけなかった。
流れ流れて、やっと見つけた商売が氷屋であった。
それで、田舎に置いていた我々家族を東京に呼び寄せたのであった。
電気冷蔵庫などなかった時代である。
一般家庭の冷蔵庫は、氷を入れて冷やす代物であった。
冷蔵庫の上段に1貫目(約3.75kg)の氷を入れ、
下段に飲み物や野菜を入れて冷やす仕組みになっていた。
今 では考えられない原始的な冷蔵庫だが、どの家庭にもあった。
そんな一般家庭や商店に1日2回、氷を配達するのが氷屋であった。
「涼しくていい商売だな」とお思いになるであろう。
昔も、よくそう言われた。
とんでもない誤解である。
確かに氷は冷たい。
しかし、氷は重い。そして溶けるのである。
溶けてしまえば、売り物にはならない。
いかに早く配達するかが勝負なのである。
家には住み込みの店員やバイトの学生などがいて、配達していた。
勿論、父もである。
父や住み込みの店員たちプロは、
自転車の荷台に24~36貫目(約90~135kg)もの氷を積み重ね、配達先を回る。
時間が勝負なので、坂の多い街を常に全力で漕ぐ。
過酷な商売である。
だから、同業者の大半はヤクザかその類であった。
廻りでカタギの人と言えるのは、父と後一人だけだったと記憶している。
断わっておくが、現代でも少数の氷屋さんはあるが、みなさん、まともな方ばかりである。
これは昭和30年代の話であることを認識して欲しい。
当時、商売をしている家では、小学生も高学年になれば働き手であった。
私も小学5年から配達を手伝った。
子供といえ、自転車の荷台に12貫目(約45kg)の氷を積む。
それを1日2回、毎日配達するのである。
汗まみれになりながら、必死に自転車を漕いだ。
それでも子供の悲しさ、どうしても配達が遅れ勝ちになる。
待っているお客からは、
「冷蔵庫のものが腐る」、「商売に差し支える」と叱責の嵐である。
「すみません、すみません」と頭を下げて回る毎日であった。
肉体的辛さよりも、この精神的辛さのほうがこたえた。
中には、頭をこづいたり、殴るお客さえいた。
悲しくて、辛くて、
「どうして、ウチはこんな商売なんだろう」
と、サラリーマンの家庭がうらやましくて、ならなかった。
そんなある日、新しいお客が出来て、ある団地の5階まで氷を運んでいった。
冷蔵庫に氷を入れ、お礼を言って立ち去ろうとした時、
留守番をしていた“おばあさん”が、
「ちょっと待って」と言い、なにやら私の左手に握らせたのだ。
驚いて左手を開けると、そこに100円玉が1枚あった。
「小さいのに大変だね。これで好きなものでも買ってお食べ」
おばあさんは、そう言って、両手で私の左手を包み、その100円玉を握らせた。
思いもかけない事態に、私は返す言葉も見つからず、
黙って頭を下げると、階段を駆け下りていった。
下まで一気に駆け下りて、自転車のところに戻ると、涙が溢れた。
私は、涙を流しながら立ち尽くしていた。
あれから半世紀が過ぎようとしている。
それでも、左手に残る100円玉の感触は消えることがない。
悪いことに手を染める度に左の手のひらが熱くなる。
100円玉の感触は、時にやさしく、時に厳しく自分を導き、慈しんできたように感じる。
今回は、「思考を鍛える」主題から外れた話になってしまったが、
思考の奥底の深いところに、どんな経験・想いがあるかは重要である。
それが、かなりの強さで自分の思考を引っ張るからである。
<エピローグ>
もう名前も忘れてしまったおばあさんは、当然、この世にはいない。
あの世で再会できる保証はないが、
もし出来たら、改めて「ありがとうございました」と言いたい。
だいたい、他人の思い出話など「つまらん」ものの代表なので、
「きっとパスされる」と自虐的には思っている。
まあ・・・とにかく話を始めるとしよう。
昭和30年代の話である。
近年、映画がヒットした「always 三丁目の夕日」の世界である。
小雪や堀北真希の顔でも思い浮かべれば、
少しは読んでもらえるかな、などと思いつつ話を進める。
商店街と住宅街が入り混じる、とある街の坂道を、
小学6年の私は必死に荷物用の重い自転車を漕いでいた。
真夏の太陽が容赦なく照り付ける、うだるような昼下がりであった。
その頃、私の家は氷屋を営んでいた。
職業軍人であった父は、戦後、米軍の公職追放令によって、まともな職に就けなかった。
郷里で商売を始めたが、何をやっても武士の商法。
借金ばかりが膨れ上がり、故郷を捨てた。
単身、東京に出た父だが、思うような商売にありつけなかった。
流れ流れて、やっと見つけた商売が氷屋であった。
それで、田舎に置いていた我々家族を東京に呼び寄せたのであった。
電気冷蔵庫などなかった時代である。
一般家庭の冷蔵庫は、氷を入れて冷やす代物であった。
冷蔵庫の上段に1貫目(約3.75kg)の氷を入れ、
下段に飲み物や野菜を入れて冷やす仕組みになっていた。
今 では考えられない原始的な冷蔵庫だが、どの家庭にもあった。
そんな一般家庭や商店に1日2回、氷を配達するのが氷屋であった。
「涼しくていい商売だな」とお思いになるであろう。
昔も、よくそう言われた。
とんでもない誤解である。
確かに氷は冷たい。
しかし、氷は重い。そして溶けるのである。
溶けてしまえば、売り物にはならない。
いかに早く配達するかが勝負なのである。
家には住み込みの店員やバイトの学生などがいて、配達していた。
勿論、父もである。
父や住み込みの店員たちプロは、
自転車の荷台に24~36貫目(約90~135kg)もの氷を積み重ね、配達先を回る。
時間が勝負なので、坂の多い街を常に全力で漕ぐ。
過酷な商売である。
だから、同業者の大半はヤクザかその類であった。
廻りでカタギの人と言えるのは、父と後一人だけだったと記憶している。
断わっておくが、現代でも少数の氷屋さんはあるが、みなさん、まともな方ばかりである。
これは昭和30年代の話であることを認識して欲しい。
当時、商売をしている家では、小学生も高学年になれば働き手であった。
私も小学5年から配達を手伝った。
子供といえ、自転車の荷台に12貫目(約45kg)の氷を積む。
それを1日2回、毎日配達するのである。
汗まみれになりながら、必死に自転車を漕いだ。
それでも子供の悲しさ、どうしても配達が遅れ勝ちになる。
待っているお客からは、
「冷蔵庫のものが腐る」、「商売に差し支える」と叱責の嵐である。
「すみません、すみません」と頭を下げて回る毎日であった。
肉体的辛さよりも、この精神的辛さのほうがこたえた。
中には、頭をこづいたり、殴るお客さえいた。
悲しくて、辛くて、
「どうして、ウチはこんな商売なんだろう」
と、サラリーマンの家庭がうらやましくて、ならなかった。
そんなある日、新しいお客が出来て、ある団地の5階まで氷を運んでいった。
冷蔵庫に氷を入れ、お礼を言って立ち去ろうとした時、
留守番をしていた“おばあさん”が、
「ちょっと待って」と言い、なにやら私の左手に握らせたのだ。
驚いて左手を開けると、そこに100円玉が1枚あった。
「小さいのに大変だね。これで好きなものでも買ってお食べ」
おばあさんは、そう言って、両手で私の左手を包み、その100円玉を握らせた。
思いもかけない事態に、私は返す言葉も見つからず、
黙って頭を下げると、階段を駆け下りていった。
下まで一気に駆け下りて、自転車のところに戻ると、涙が溢れた。
私は、涙を流しながら立ち尽くしていた。
あれから半世紀が過ぎようとしている。
それでも、左手に残る100円玉の感触は消えることがない。
悪いことに手を染める度に左の手のひらが熱くなる。
100円玉の感触は、時にやさしく、時に厳しく自分を導き、慈しんできたように感じる。
今回は、「思考を鍛える」主題から外れた話になってしまったが、
思考の奥底の深いところに、どんな経験・想いがあるかは重要である。
それが、かなりの強さで自分の思考を引っ張るからである。
<エピローグ>
もう名前も忘れてしまったおばあさんは、当然、この世にはいない。
あの世で再会できる保証はないが、
もし出来たら、改めて「ありがとうございました」と言いたい。